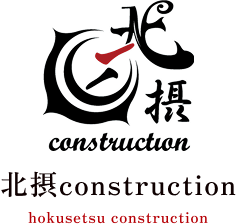二季化する“熱中症リスク”と向き合う建設業
建設業の現場が
取るべき新たな対策とは
近年、「熱中症」といえば真夏のリスクと
されてきましたが、
注目されています。
本記事では、
「熱中症の二季化」がなぜ起きているのか、
その背景となる法的・気象的知識について解説します。

熱中症は
“夏だけのリスク”ではない
従来、熱中症は「梅雨明け~8月中旬」
しかし最近では、
救急搬送が増加しており、
「2023年の5月~
(出典:総務省消防庁「熱中症による救急搬送状況」より)
という状況が報告されています。
この傾向は、
地球温暖化に伴う「季節の境界の曖昧化」、
高温多湿の長期化に起因しています。

建設業・法面工事での
“二季化熱中症”の具体的リスク
1. 暑さに身体が
慣れていない時期の発症
5月や9月の熱中症の多くは、
「
ことが原因です。
法面作業では、
高所で風通しが良いと思われがちですが、
長時間身体を動かすことが多く、
2. “暑熱順化”の
タイミングを誤るリスク
熱中症に耐える身体をつくる「暑熱順化」は、
数日~
ところが、5月や9月は
「今日は涼しいが明日は真夏日」
気候の乱高下が激しく、
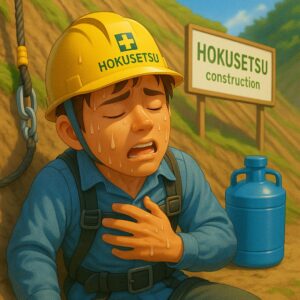
北摂constructionの
現場で行っている対策
■ 春・秋でも“夏季対策”を継続
北摂constructionでは、4月末~
以下の熱中症警戒強化月間として対策を行ってい
• 朝礼時のWBGT値(暑さ指数)計測と共有
• 水分・塩分補給タイム(30分~1時間おき)
• 空調服・ファン付きベストの着用義務化
• 休憩所にはスポーツドリンク・氷を常備
• 日陰スペースや簡易テントの仮設
さらに作業時間の調整(早出・早上がり)や、
されているためです。
(

法面工事に特化した対策の工夫
法面工事では、
通常の建設現場よりも体力の消耗が激
熱中症のリスクも倍増します。
北摂constructionでは、
• 親綱にぶら下がる作業員の休憩インターバル管理
• 法面の“日陰になる方向”を意識した工程調整
• 散水車での法面冷却作業(一部現場)
• 個人の体調チェックアプリの導入(現場単位での試験運用)
これらは単なる“夏季限定策”ではなく、
春・

高齢作業員への配慮も不可欠
近年の建設業では、
そのため北摂constructionでは、
5月・9月も“夏季就労制限”を実施し、
• 午前中中心の勤務(13時完全撤収)
• 休憩回数の増加・階層移動時の補助人員配置
• 体調報告カードでの当日コンディション確認
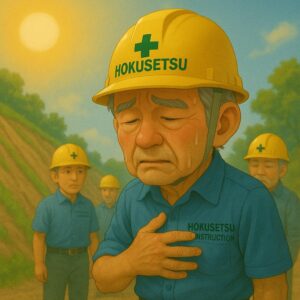
建設業界全体が
“熱中症の二季化”に
どう備えるか
このような気候変動のなか、
「働き方改革+暑さ対策」
以下のような動きが出ています。
• 「建設業の熱中症ガイドライン2023」の改訂
(国交省)
• 現場単位でのWBGT計測の義務化検討
• 熱中症発症後の迅速な報告体制の整備
(労災補償にも関係)
北摂constructionでは、
“安全と効率”

まとめ
“二季化”の意識が、
現場の命を守る
熱中症は「真夏のリスク」から、
「春秋を含む長期リスク」
特に屋外の法面工事や建設業現場においては、
北摂constructionでは、経験や慣習に頼らず、
これからの建設現場には、「二季化熱中症」という
新たな視点と、

【参考文献・出典】
• 総務省消防庁
「令和5年(2023年)
• 厚生労働省
「職場における熱中症予防対策マニュアル」
• 国土交通省
「建設現場の熱中症対策ガイドライン2023」
• 日本気象協会「熱中症ゼロへ」プロジェクト